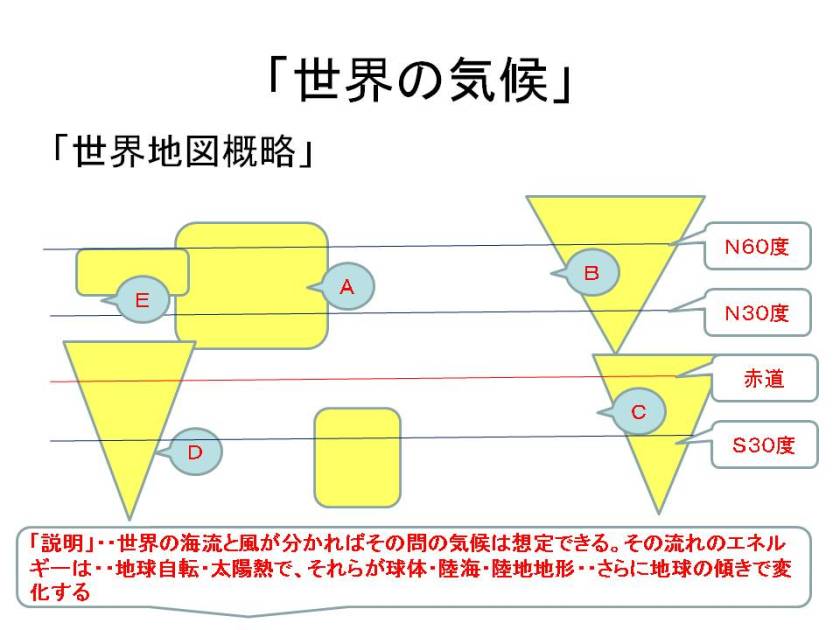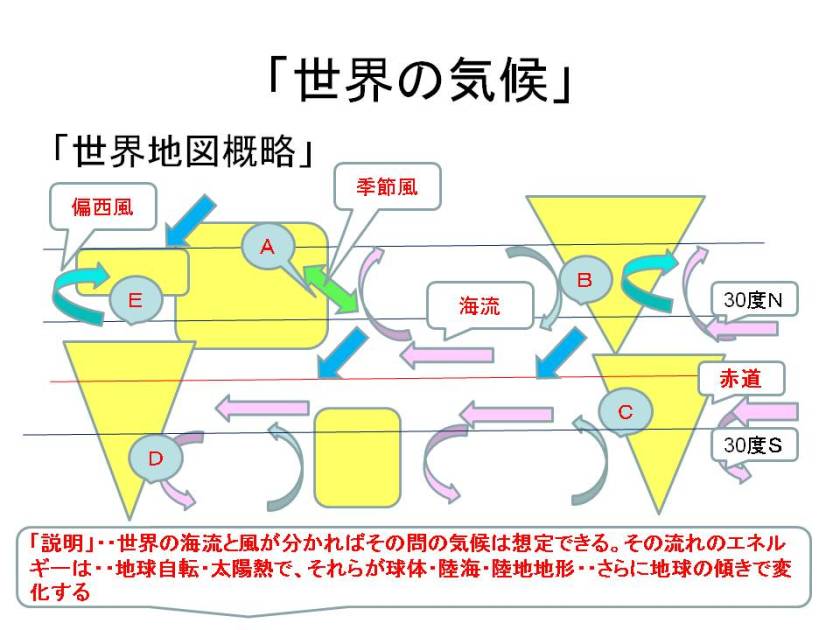・・「お知らせ」・・
このブログのほかに「HP」を作りました・・幾分か読みやすくするためですが、内容はほぼ同じです・・
そして、これからの記述は「HP」の方へと移りたいと思いますので、関心のある方は、これからは「HP」の方へ来てください。
URL goldenhillweb.amebaownd.com です
「第3話」・・「重層柔構造」の実践・・具体化を考える
組織の硬直化を防ぐための適正な形態が「重層柔構造」であることをこれまで述べて来ましたので、ここではその具体的な実践について検討してみましよう。
◎「重層柔構造」・・「重層構造」をつなぐ「柔」な小組織の具体・・
これまで述べてきたように、組織は自由フラットでも縦の秩序制でも不十分であり、この2つの組織の合体が望ましいのであるが、それぞれ相反する性質の組織の結びつきは難しい。そこで、どの組織でもこの融合のための工夫を行っている。今回のテーマではこうした工夫について検討してみよう。・・ポイントは、「対流」と「交流」である・・「意見対流」「人事対流」(上下対流)、「意見交流」「人事交流」(相互交流)・・
「CEOs」(執行グループ・・「管理職」という名称では組織員管理を主な仕事とすると思われるが現代の変動期の組織では「執行職」としての役割が大きいのでこの名称とした)・・組織のトップ集団であり、「構想」(「理念」や「組織の基本的仕組み」)について思考し、決定する組織であることから非常に重要な所です。しかし、それだけに権限が利権を生み、その利権の所有に特定グループが群がり、組織を食い物にする危険性があります。歴史上の権力者達が陥った道です。
古くは、この権力集団は、特定家族・親族、特権身分として過ちを繰り返したのですが、イギリスなどでの市民達が選挙による政権交代を常態化するシステムを作って、こうした過ちを防止することとなった。その結果、この新しいモデルが旧態モデルを凌駕して現代に至っています。でも、こうして現代化した組織でも、その内部には、やはり「身内意識」があります。それがファミリーだけであると旧体質すぎて淘汰されてきていますが、学閥・職域系列などは存在しています。そして、前近代的な血縁・地縁の人事硬直化から抜け出た現代的な組織でも、前述したように学校系列や職場系列での人事硬直化を起こします。系列は、その組織の制度や文化保持には必要なものですから全く否定されると混乱が起こります。このように単純に割り切れない、複雑系の状態が実際の経営では難しいところです。
そこで、通常の人事は、制度や文化保持のために、執行組織の周辺にいる人を順次入れ替えるのですが、・・その方が安定性があるのでそうするのですが・・系列化が新しい状況対応に効果的でないと思われるときには、系列外からの人事配置となります。・・前回の話題提供で述べたように、これを日下公人氏は「人事破壊」としています・・ただし、このような破壊的人事劇は頻繁に行うことは危険度の高いことなので、賢い組織はそれなりの工夫を行います。これが、「柔組織」の設置です。執行組織に「TT:シンクタンク」を付属させ、そこからの「意見対流」を行い、情報と知識や理論を活性化します。また、外部組織からの人材を「人事交流」として社外役員などとして迎え、アドバイザーとして「意見交流」を図り、より幅広い所見を得るようにしています。さらには「PT:プロジェクトチーム」による活力ある提言、「TP:サードプレイス」での自由な意見の対流と交流も望まれることです。
このような工夫が行われない組織では、先の言葉での「責任感で安定した組織が、速くも官僚化に向かう」こととなります。・・これについてはこれまで多くを述べましたが、ポイントは「責任感・・自己防衛・・規格人」という組織文化や人の意識の変化、それによる「組織の硬直化・・新企画は無し・対応力は弱い」の状態です。・・こうした状態の組織ではハードランニングに追い込まれることとなります。
☆「TT・PT・TP」に関わる「工夫の具体」について見聞したものを述べてみましょう。
~組織内での自由提言を核にして、そこに賛同者が集まり、認知されれば「PT」が結成される。また、「TP」もこうした提言から設置される。・・・この承認・認知は執行役員や組織中堅役員が「TT(シンクタンク)」での検討を参考により行われる。~
・・具体的な方策はささいなものですが、このような「TT・PT・TP 柔組織」での活動が組織員の活性化を進めることとなりますし、こうした方策が提言される組織(ここでは学校)のあり方そのものが「柔」構造でもあるのです・・
*「TT・PT」への生徒会の参画構想~学校経営のある場面(生徒・学生行事)には生徒・学生の代表者が参加している・・「人事対流」がここまで進むことと改革・改善は進む (TT・PT)
・・このためには日頃からの「TT」での生徒・学生代表の研修・研究が求められます・・
*「金魚育成プロジェクト」~ある学校では10年来の育成を誇る (PT)
・・「10年飼育」の奥にある職員・生徒・保護者の参加と連係した協力・その尽力がその奥にある良好な学校組織だ・・
*「間引き苗」育成計画~障害児学校での花壇作成・・ (PT)
・・植え付け時に,指導の庭師が不出来苗を選別して捨てるよう指事したが、生徒達が涙する(「私達みたいだ」と)・・そこでこの苗を育成するプロジェクトを結成した・・
*「エントリー制掃除担当」・・希望者による掃除担当の分担・・義務ではなく,学校への愛着・愛校心から主体的に掃除をしようとするしくみ造りである・・(PT)
*空き地での野菜畑プロジェクト~学生・生徒が自発的に校内の空き地を畑にした (PT)
・・当初は許可なく行っていたが、「企画書」を提出することで認可されたプロジェクトとなる・・
*夏休み花壇水遣りプロジェクト~小学校生徒(児童)・保護者が夏休みに輪番で学校花壇に水遣りに・・その時に家のクーラーは切って外出の約束をすることで省エネにも・・(PT)
*家庭クラブ弁当作成プロジェクト~地域農家との共同により弁当の販売・・学校行事の時に、参加者から注文を受ける・・「地産地消」の弁当造りの取り組み・・(PT)
*卒業生残し靴・体操服の援助ボランティア・・生徒会が実行 ・・(PT)・・残された靴やジャージの再活用・・途上国への支援へ・・

*「生徒作品オークション」・・生徒達の作品を売り出し・保護者や地域の人が購入・・生徒会費に納入(アメリカンスクールでの発案) (PT)
☆「TP:サードプレイス」(「自由な第三の場」)関係
*「言いたいこと飛行機」・・自分の本音を書いた紙を飛行機にして飛ばす大会・・(PT・TP)
・・「夢・希望」「困ったこと・訴えたいこと」「感謝の気持ち」を紙に書いて飛ばす・・匿名自由である・・(「アンケート」より本音が出せる,明るく広い気持ちにもなれるかもしれない)
*「自由喫茶室」や「コーヒー飲み場」=保護者・OB・OG、職員の自由参加・自由発言が促される場の設定・・「斜めからの目線」となる・・東京S区W中学校 (TP)
*「組織内ニックネーム」=「公式ネームプレート」の横に「ニックネーム」を記して,一定日・時間には自由な人間関係でのコミュニケーション・・R製薬 (TP)
*「職場対抗運動会」・・綱引きチーム結成・・職種・階層を超えたグループの結成・・職場の風通しが進む ・・D工業 (TP)
*「フラット机での事務業務」・・円型机・役職に関わりない椅子の配置・・その日毎に役職に関わりなく自由に座る・・相互コミュニケーションが緻密判断・決定も速い ・・M工業 (TP・PT)
*「組織内ニックネーム」=「公式ネームプレート」の横に「ニックネーム」を記して,一定日・一定時間には自由な人間関係でのコミュニケーションを行う・・R製薬・・(TP)
*「黙示啓発・内発(教育)」=事業所・学校での,玄関・庭園・廊下などに自然物・文化物などを設置や掲示する・・「ものは言わない」(「黙示」)がそれとなく雰囲気として啓発するもの (TP)・・ 花木や俳句・川柳,絵などの展示。それには,建前的なものではなくより内面的なものに。・・(G高校では売店が主催する「売店川柳会」 *「『誉めカード』発行・掲示 *「『さしすせそ発言』プレート」(さすが・知らなかったよ・すごいな・センスいい・そうだね)設置など
*「学校ネコ」や「学校犬」などの飼育・・有志責任グループによる飼育を前提として責任を持たせる。(C生徒会からの自由発案・・残念ながら実現はしていないが・・)
*「理想の職員室」プラン・・10年前の希望プラン(「図を参考」)であるが、ここではフォーマル(通常の会議室で公的な業務執行)とインフォーマル(小会議室で自由さとフラットさで本音的な相談が可能)の調和が良い・・
(補足1)重層柔構造組織(知恵・予見・提言のある組織)」の具体・・物語風
~「ある重層柔構造組織でのAさんの活動から考える」~
Aさんは,昨日から気にかかっていた問題について自分なりに考えて,まず,朝の顔合わせで,同僚のBさんに,昨日の課題の疑問点と自分の感想と意見を述べて,自分の対応の仕方を相談しました。その際に,彼女も同僚のBさんも,まずは組織のルールを意識しての公式的な対応を想定しながら思考して一応の解決策を出し,空き時間に上司であるグループ長のCさんに報告し,午後のグループミーテイングにそれを提示し,グループ内での共有化を図ることにしました。
そのミーテイングでは,当初は,皆がそれを妥当だとして承諾しょうとしましたが,Eさんが「ルールではそうなのだが,何か腑に落ちないのよ」と言い,自分の疑問を述べ始めたのです。実は,Aさんも,心の底では自分の出した対応策に納得はしていなかったのだが,当事者としてはそうした疑問を言い出しにくかったのです。この件は,組織のルールのあり方に関わることにもなり,この日のグループ会議では結論が出せず,「シンクタンク」に検討を提起するよう,グループ長のCさんは執行役員のDさんに報告と相談に出向くこととなりました。
そこで,翌日「シンクタンク」の会合が招集されました。このシンクタンクは,組織内の人事配置・性別・年齢構成をある程度考慮して形成されており,組織のミッションの作成や検討を担い,またマネジメントのやり方についても現場からの提言を受けながらそれを検証する権限を持つものです。この「シンクタンク」からの提言はトップ層である執行役員も尊重して,組織改善に努めます。この任期は3年です。実は,Aさん自身も昨年からこの会の若手メンバーに選出されて,これまで様々な研修や研究を行ってきております。Aさん自身は,自分の専門は言語学ですが,歴史的な古典的な文献や将来予見に関わる本を紹介されて読んできました。そのお陰で,幾分視野が広がったようにも思いますが,まだ30歳,仕事経験はある程度はありますが,人生経験は充分ではないために,それほどの確信があるわけではありせん。そのため,ついつい先輩の理論と経験からの判断に追随しがちになるのですが,その「シンクタンク」には,この組織外からも2名のメンバーが来ており,とかく内向的・主観的な議論になるところに外部からの客観的な視点から議論を大きく広げるための意見を出しますので,Aさんも別な思考と判断について知ることが可能となっております。現状の勤務の関係で,現役者を2名そろえるのは困難で,そのうちの1名はすでに退職して勤務はフリーな人ですが,それはそれなりに時間軸を広げる役目を担っております。
また,この組織では,「シンクタンク」だけでは,どうしても思念型になりがちなので,現場からの実践とそれによる提言を明確にできるよう,「プロジェクトチーム」の育成も推進しています。これは,日常の業務の中での改善策や新しいアイディアの試行を行うものですが,これにはそうした策やアイディアを提唱した人が中心となり賛同する人がメンバーとなり結成されたものです。ここでも,組織の既存のルールにも挑戦する思考も許され,実践については執行役員の許可を得れば試験的に行うことも可能なのです。Eさんは,自分でこのプロジェクトを立ち上げた人で,現場での自分の思いや感性を重視するタイプの人です。 さて、先の提案を受けて、「シンクタンク」は,これまでの組織ルールでは充分な対応ができないことと判断し、一部の組織改革を行うことにしました。それにより、Aさんも現場対応の活動がとれるようになりました。
この組織が画期的なのは,「建前議論で人を縛らない」ことを重視していることです。「参加者がそれを納得する過程が組織の強さである」と認め、「建前だけでは本当の納得ではない」ことにも気付いています。それには,当然その前提として,「建て前」としての組織のミッションの意義と役割を尊重し,そのミッションが空洞化しないためには,その内実の充実が必要だという組織的意思が組織のトップ層にあるのです。彼らは,自分たちの組織が行う仕事が社会に持つ意義と役割をいつも検討して,そのための組織制度はこれが最善であると自信を持てるだけの日々の検討を繰り返しているのです。この執行役員たちトップ層のこうした自信の裏には,先ほどの「シンクタンク」や「プロジェクトチーム」の活動との連係があるのです。
実は,この組織も,これまでにはそれ相応の道程がありました。組織の建て前のミッションさえなく個々人の思い思いで,参加者の「数の論理」でものを決めていた時期。その後,その反動で,トップ層が「専一的」に判断・決定し,トップダウンしていた時期。この「2つの痛い失敗」(「大衆迎合型」と「トップ専横型」)があったのです。
しかし,その後,この組織はこれらの失敗を糧にして堅実・健全な組織改革を行い,数々の工夫もしてきました。大きな組織改革はこれまで何度の述べた「重層柔構造」の制度と文化です。そして,この重層柔文化を日常に定着するため,つまり,「組織と自分」の両立を意図して,組織員のネームプレートにも工夫をしています。それは,公式職名と併せて組織内ニックネームを併記するものです。公式の仕事関係は役職名と本名で呼び合いますが、「TP」の「場」では、組織ルールとは異なっていても自分の「本音」からの思いを述べますが、その時にはニックネームで呼びかけます。時々混同も起きますが,最近は大分定着したようです。「TP・第三の場」としての喫茶室では,ニックネームを使っての自由な意見交流・対流が行われていまので、そこでは,「実はこんな場面を見たのだけど・・」「皆は000だと言っているが,本当に皆そう思っているの?」「今こういうことだけど、もっとこうしたら良いのでは・・」などの,気付きや意見が出しやすいのです。そして,案外とこうした会話が,組織内の「常識的見方」や「無理やり合意」(これにはトップからの抑圧と同僚からのピアープレッシャーによる自己抑制から起こります)の問題点を明らかにします。このお陰で、裏で行われていた陰湿な仲間外しも明らかになりましたし、数人の下積みの努力も顕彰されました。
そして,こうすることによって,「第一の場」(公的職場)での討議が,逆に明確になってきました。この場では,職名と立場を明確にしたうえでの議論となるのですが,「第三の場」での本音トークによる一定の納得の上での組織ルールの是認となっていますので,これまで以上にこの組織ルールの尊重意識は高まってきています。もちろん,ルールや組織決定への疑問があればまた,それなりの本音トークを行い,一定の方向が出れば,公的なルートで「シンクタンク」での検討を進めます。このような柔軟組織運営が保証されていることから,組織への愛着と信頼はこれまで以上に高まっています。
そして,こうした組織の制度と文化は,他の下部組織(「企業なら関連組織」,学校なら「生徒会組織」・「保護者組織」)にも適用します。そうすることで,この下部組織が活性化し,そこから新しい提言が出てきますので,組織全体としては大きな力量アップになりますし,外部対応の機能化はもちろん内部敵対行動や不祥事などが事前に解消したり防止できたりして,危機管理能力が高まります。
(補足2)「VSOP表」:「人材育成」とその到達評価について次の表を参考にして欲しい。
~ VS段階では,「人材」育成レベルであるが,OP段階となると次第に「人(人格)」育成の要素が強まっていく ~
「教職の仕事力の成長・・『研修から学習・研究』へ」・・生活と学習・経営領域での検討・・
| 成長段階 | 職員資質成長課題 | 生徒指導・生活文化,生徒会の育成力を身につける | 学習文化の育成力を身につける | 組織経営力・他組織との連携力を身につける |
| Ⅳ期
50歳台 |
P
人間性・大きな見地から仕事に取り組む |
◎「生活文化習熟」
講話・説話ができる ◎生徒には「許す」・「受け止める」内面的な対話力」・・「心の背景へ」*問題生徒の受容と指導*後輩教師の指導 |
「学問からの発想」
◎真理探究・仮説設定力などの「学習文化」を育成する・「学習講座」が開ける ◎「自作参考書」「学習指導書」の発刊 |
◎「長期展望・人間育成からの発信」
*人が育つことが実績に繋がることの把握・発信 *「組織論」「人間論」に関わる著述・講師を務める。 |
| Ⅲ期
40歳台 |
O
グループのリーダーとなれる |
◎「生活文化指導」
茶と華の基本指導 ◎生徒には「諭す」・「つながり作り」「心へ」 ◎「生徒育成の理論と実践」の指導 *主任的な役割・研究会・研修の講師に |
「学問探究と学習の合体」
◎学習理論の奥行き作り *理論研究の推進 *「自作問題集」の発刊 *「研究誌に小論文を」 ◎「学習研究会」の立ち上げ・リーダーに |
◎「経営全体からの発信」
*経営理念とマネジメントの力量=「理念・組織制度・人・環境」の総体から考え,組織総体での改善策を提示することができる。 *研修のチーフとなる。 |
| Ⅱ期
30歳台 |
S
専門職の意志と技能を深化 |
◎「生活文化修得」
◎「叱る」・「語れる」 *生徒への対応・・明確なnoとyes 「態度への関心」 ◎「生徒会・クラス育成理論を学ぶ」 *理論的研修=読書,先輩・上司と連携 |
「教科10年の後期」
◎「学問探究」の継続 教材開発力と学問研究の一致 *「自作サブノート作成」 ◎「教え方・学び方研修」 *学習心理・評価・組織論の研究,質問できる勇気 |
◎「経営合理からの発信」
*理念構想の検討を行う。(組織総体のあり方の研修・古典の智恵・他校研修)*経営的視点=投下量と成果関係を理解(「マネジメント系の理論研修」) *講師として,問題点の改善案を提起できる。 |
| Ⅰ期
20歳台 |
V
職業への情熱と先輩・同輩から学ぶ姿勢 基本的な職業技能を修得 |
◎「生活文化修養」
礼儀・清掃文化の修養・校歌習得 ◎生徒の中に入る「率直に怒る」・「共に汗を流す」*生徒に率直 「行為への関心」 ◎「生徒会・クラス育成の実践研修」 *実践しながら理論を |
「教科10年の始まり・とにかく学ぶ」・・教えることは学ぶこと
◎「勉強と学問との両立を」・学問を忘れない *大学時代の書物を保持*教科書・参考書を徹底学習 ◎先輩教師から学ぶ・・徹底質問できる素直さ |
◎「経営への関心・発信への意欲」・・仕事の構造を理解する
*組織は,「理念・目標・制度・人・設備・資金」からなることの理解 *仕事と職場を好きになる *現場への溶け込み・学び |
V:vitality S:specialist O:organizer P:personality


 「説明」・・1:「身体構造」は次の3組織です。
「説明」・・1:「身体構造」は次の3組織です。
 「説明」・・「研修と学習」
「説明」・・「研修と学習」 「説明」・・
「説明」・・