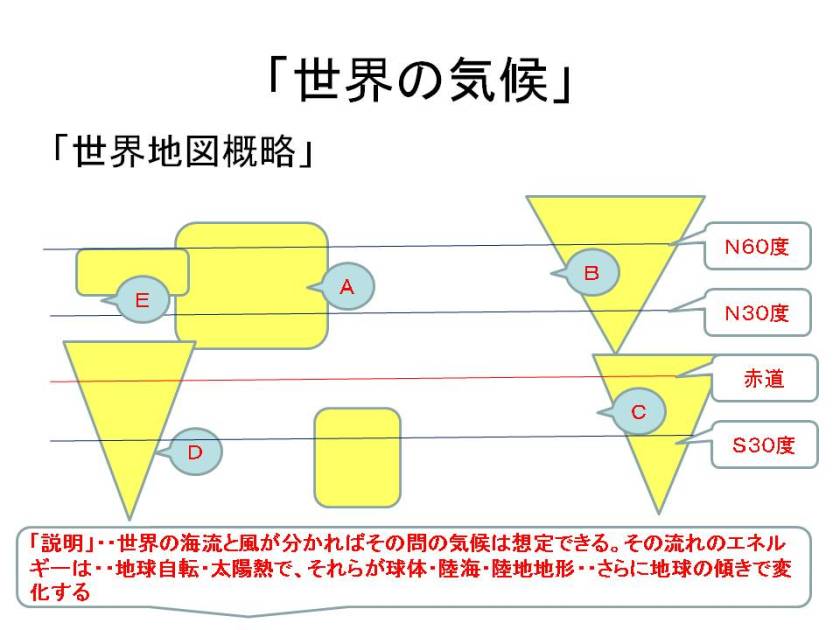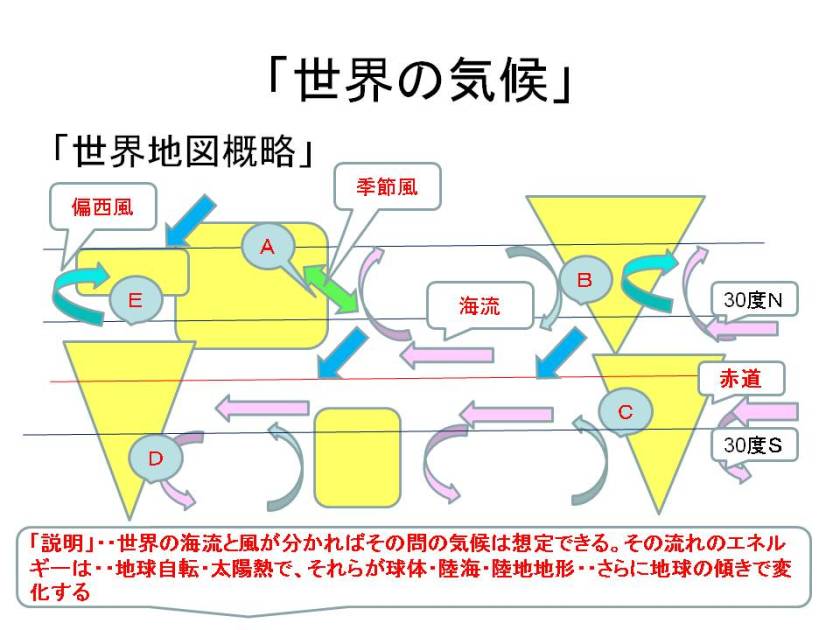~ ブログ「第3部」を始めるにあたって ~
今年古希を迎え、人生のほぼ終了期の始まりとなりました。古代インドでの区分けでは、古希は、林棲期(家庭・仕事の暮らしを引退し森で暮らす時)から遊行期(人生の最後の旅)に向かう齢だそうです。現代の平均寿命からすると古希はまだ未練がある歳で、私も人生を悟ることはないのですが、そろそろ限界点が来るだろうとは思っております。
そこで、これまでの仕事の一定の整理をしようとの思いで「ブログ」を始めました。この中に自分の思考・実践したことを書くことで、もしかして後世の人に何かの役立つことがあれば幸いだとやや純粋に思えるようになってきました。
もし、このブログの内容を40歳台で把握していれば子供に伝授できたのですが、60歳台にやっと体系立てた叙述が可能となってしまいました。孫達に直接に「面授口説」で伝えたいと思うのですが、まだその歳にはなっていませんし、孫達がその歳になった時には私の方が怪しくなっています。そこで仕方なく「文授筆説」(?)としての「ブログ」ということになり、また、伝える人も孫世代の子供や彼らを導く親や指導者の多くの方にも拡げたいとも思うようになりました。
「ブログ」は提示する方も受け取る方も、互いに意見も感想もなしという状態にすることで、自由な関係が保たれるようです。本やCDなどでは、双方の関係が明確で押しつけがましくなります。(時には本をお渡しますが双方自由な関係は要りますね・・この紙をお渡ししても同様です)
もしそういう自由な関係で、このブログを読まれようとする方は次のアドレスに来てみてください。
・・「goldenhillweb.wordpress.com」・・Googlです
「思考力入門」(「学習論」「組織論」)です
なお、読みやすいのは「第3部」からです
金岡 俊信(goldenhill)より
第3部 「組織論」・・その1」
・・なお、第3部のテーマは個別にしますが、内容は1部・2部と重なりますのでその点はご容赦ください・・また、その意味では、1部と2部は小難しいのでこの3部からお読み頂いても内容としては同等です・・
今回のブログ・・「組織の盛衰」から人事を考える
・・今回のテーマでは、『組織の盛衰』(境屋太一)、『人事破壊』(日下公人著)を参考に「H県K委員会人事交替劇」を考える・・
「会社は夢で始まり,情熱で大きくなり,責任感で安定し,官僚化でダメになる」
坂本幸雄(元 エルピーダメモリー社長)
この言葉と似たようなものとして,「築城3年,落城3日」というものもあります。私達人間は,人が互いに集まって組織を作りながら生き抜いてきたのですが、しかし,この組織が終末期になると、人を追い詰めていく。創成期の,活き活きとした人々の集まりが,それなりの混乱と内部対立期を経て,組織的発展をして成功するに従って,この成功体験にすがった指導層の硬直化で、組織の官僚化が進み、人が活き活きと生きられなくなってくるのです。先のこの言葉は、それをうまく表現していて、ある先生から聴いたときにすぐに耳に残りました。
様々な組織の関わる問題を考える場合にも,こうした組織の在り方の変化から検討してみることが必要と考えます。例えば,かつて私の所属していた「学校組織」では、いじめや不登校,各種ハラスメントへの対応,さらに外部からの危機への対策が、組織的な欠陥(内部連係の不足や形骸化した対応)により混迷に陥る場合があります。組織が有効に機能するようにするためにはどうしたらよいのか,組織の人間関係の「しくみ」(システム)とそこでの「人間存在」(文化・意識)から検討してみたいと思います。
「第Ⅰ話」・・・「組織とは」
~人はなぜ組織を作ったのか、そしてその組織がなぜ人を活かせなくなるのか~
1:組織のはじまりから成長・発展
人は孤立すると弱い。今、人口減少で多くの地方が孤立した老人問題を抱えている。それでも、現在は文明利器(この奥には「人間集団がある」)のお陰で、一人でも生き延びられる。もし、遙か昔、人間集団が文明の利器を生みだしていないときのことを想像すると、この自然の中で孤立して生き延びることは難しいと思えます。
「図式・・組織の成立と発展・人の意識」 「説明」・・組織の始まりは、ただ集まっただけの「集合」段階で、そこでは人は「個人」としての自主性を持つがまとまりがなく、組織的決定や他の集団との競合では弱い。そこで自分をある程度抑えて一定のまとまりを持つ「集団」へと転換が行われる。さらには、この集団を明確なルールと約束によって機能的なものとすれば「組織」が成立する。この段階で組織は大きく成長し、人は「人材」として組織対応力を持つ。だがこのやや成功した段階では組織は保身的になりがちで硬直化が進みます。そこでは、上層部での専横が起こり、中間層は保身に、普通の組織構成員は自己防衛に走ります。組織の推定と崩壊の始まりです。
「説明」・・組織の始まりは、ただ集まっただけの「集合」段階で、そこでは人は「個人」としての自主性を持つがまとまりがなく、組織的決定や他の集団との競合では弱い。そこで自分をある程度抑えて一定のまとまりを持つ「集団」へと転換が行われる。さらには、この集団を明確なルールと約束によって機能的なものとすれば「組織」が成立する。この段階で組織は大きく成長し、人は「人材」として組織対応力を持つ。だがこのやや成功した段階では組織は保身的になりがちで硬直化が進みます。そこでは、上層部での専横が起こり、中間層は保身に、普通の組織構成員は自己防衛に走ります。組織の推定と崩壊の始まりです。
◎「はじまり」
組織は「利害・感情・理想」の要素を持つといわれますが、最初の組織はとにかく「生存という利害」から始まったと思えます。生き残りのために人は結びつかなければならなかったのでしょう。最初は、「自然・他動物」に対し、次いで、人口が増えると他の「人集団」に対して。その時に、「利害関係」だけでの結びつきではその組織・グループは弱いものとなります。特に、「人集団」との競合では、利害関係の切り崩しに合いますので、損得だけの集団は離合集散を繰り返します。
◎「成長」
そこで、結びつきを強めるために「情感」の要素が入ってきます。互いに好感情を持っていれば、少しの損害なら耐えてその集団にとどまります。血縁関係や地縁関係が重視されるようになります。その中で、特に強い関係を持つ集団が上層階級を作りました。古代からの王制や貴族制度がこれです。今でも、こうした集団はファミリーとして特権階級を形成しがちです。
◎「発展・・そして官僚化へ」
そして近代になると、人間の活動が大きく複雑になり、より大きなグループ・社会集団が必要となってきました。そうすると、小さな利害関係やファミリー的な情感だけでつながるわけにはいかなくなり、何かの「理論や理念・理想」により大きな集団をまとめることが不可欠となります。「GD」(グランド・デザイン)を持った社会集団です。この集団は、大きな利害関係からなっているのでときには小さな利害関係は犠牲になることもありますし、狭い情感も抑えなければならないときもあります。
大きくて高い理念がそこにあるので、小さな利害関係や感情のもつれからのいざこざは抑制されます。でも、「高い理念」ということは直接的な現場から遊離していることを意味しますので、ときには理念自体が独りよがりな動きを起こします。特に、その「GD」の奥に、何らかの特権的な集団の利害や情感が隠されている場合には要注意です。歴史上の悲劇のほとんどがここから生まれています。また、先の組織盛衰の言葉での「官僚化」の状態もこの頃に起きています。現場から離れた人材が理念に引きずられたり、理念を操る上層階層の指示に従ってしまうことによります。
◎「人材の硬直化」
組織は巨大化すると、それを維持するためにも、さらに他の組織と競合して勝ち抜くために、制度・システムを確立し、そこでの人材を育成する研修制度も整備していきます。システムは精緻になり、過ちなく、ゆとりなく運営されることになり、人は、組織人材として育成され、その職能に応じた責任を担うことを要求されます。それによって、この組織はさらなる発展をします。自由フラットな組織ではまとまりが付かないので、内部のいざこざの調整ができにくく、また、外部対応では競争・戦闘力が落ちてしまいます。そこで、秩序統制型の組織が求められます。これにより、一時は調整力のある機能的な組織になるのですが、組織の巨大化によって、秩序統制型の部門が大きくなり、さらに現場から遠のくことによって官僚型になっていきます。
また、組織が、それなりの発展をして形を整えますと、そこにいる人間を、「生の人間」から次第に「組織に適合した人材」として育成し、さらには、もっと組織的に動くように「組織に従属した規格人」として教育します。この「規格人」が官僚化を引き起こします。この「人材」は、その責任制度の中では自分の自主思考と判断で活動するのは危険度が高いことに気づきます。責任が「権限」としてではなく、処罰と連動した「義務」としての性格が強まると、人は自由判断をせず組織決定に従う「規格人」となります。この段階での組織で生き残るには、組織参加者は、自分の自主的な人格を抑圧し、「マニュアル」に従って生きる受動的な態度をとるようになるのです。「マニュアル」に従う行動なら、責任はマニュアル(それを作った人)にあることとなり、自分の責任回避が可能となります。
2:官僚型組織の問題
さてこのように、組織が初期の人間くさい夢やロマン、情熱の時期を経て、責任体制が確立する成功段階となると、システムの安定と人材の育成とがピークを迎えます。
「図:組織の変遷」・・夢・情熱・責任・官僚まで

「説明」・・夢から始まり、情熱で成長し、責任感で大きくなり安定度も増した組織は、ここが頂点となるが、やがて、官僚化で衰退する。その決め手はやはり「人」だ。
多くの経営陣は、システムさえ整えれば組織は成長し繁栄すると思っているが、そのシステムの中で働く人間が鍵を握っているのだ。多くの経営陣は、「人」を「個人」としてではなく「人材」さらには「規格人」とみなして重視しないことがある。「人材」としては「業績」重視であるが、「人」であることを無視しての業績優位の人材活用では、その「業績」に「人」が押しつぶされることもある。「人」が仕事をするのは、またその組織に参加するのには「業績」の前に「夢・ロマンや情熱」があるからであり、それを無視しての業績優位だと、人はそれに反発するか、または巧妙に適応して、自己防衛のため自己責任を最小にし、他者との関係を切っていくこととなる。いずれにしても、これが官僚化の道であり崩壊へとつながる。
◎「初期段階での課題」
人間くさい状態のときには、組織の問題はその人間くささから起きます。人間くささとは、素朴な人間関係から来る人情の暖かみがまだ存在していることですが、それと表裏一体で、夢とロマンの暴走や情熱のあまりの逸脱、さらには人間つながりでの情実の問題が起こります。これらは、初期段階の家族的結合の組織状態で起きます。時代的には、古い組織や古い体質を持つ保守的組織で起こりやすいものですが、人間の情感は根源的なものなので、後述するように、これが近代化を経た組織の中でも形を変えて問題を引き起こします。
◎「成功段階の課題」
*システムの硬直化・・この問題の改善を行い、合理的な組織形態にしたのが近代的組織です。前述したように、制度やシステムの合理性と人材採用と育成の合理性を行いましたので、大きな組織がスムーズに運営されることとなりました。成功段階といえます。しかし、これがやがては、システムの硬直化と人材の規格化を引き起こすのです。
システム硬直は、合理性と精緻さを求められることから起こります。対応の幅がありすぎるとそこに情実が入りやすく・・忖度もこれか・・なりますので、できるだけ画一的な対応がよいこととなります。組織システムの規則が重視され、法規法令遵守が求められる法治主義となっていきます。
*人材の硬直化・・上層部の硬直化と参加者の規格人化・・それと同時に、対応する人間も、人によって対応が異なってはいけませんので皆同じように対応することが求められます。そして、この法令遵守ができる人材育成を行いますので、組織としての信頼は増しますが、人間くささはなくなります。
「上層部の硬直化」・・上層部が固定化するのは、組織の継続性という願望や必要性があるからです。確かに、組織の信頼性を考えればトップ集団の継続性は求められることです。
前近代型での継続性は、「人」要素での継続性ですが、この組織の成功段階での継続性は「法」要素での継続性です。ここでいう「法」要素とは、制度、規則やきまりのことですから、人の属性に関わることからは自由なので、硬直化とは無縁にみえるのですが、逆に制度や規則に縛られるという硬直化を起こします。「制度や規則重視」の人材が登用されることとなり、堅い集団となります。それがさらに問題化するのは、制度・規則重視の学校系列や職場系列への傾倒が起こり、これが硬直化をさらにすすめるからです。これは、前近代的な血縁・地縁の系列ではないにしても、やはり似たような状態になります。言わば、現代型硬直化ともいえるでしょうか、この制度や規則を守るのはこの学校での学習・この職場での任務や研修を経た者達が適任であると考えることにより上層部人事が固定化され堅くなって来るのです。
(参考までに)・・組織の継続性は必要なことであり、それは組織上層部の継続性と関わります。それは、仲間や後継者の人選のときに、現在の上層部との関係性を重視することにみられます。その関係性とは、血縁・地縁、学校系列、職場系列などですが、それが文化的継続性(学校・職場などの第二次集団重視の傾向・・仏教でいう「法脈」)であるならば、継続性の中でも、人事対流や交流が起こり、硬直化にはなりにくいのですが、そこに、ある意味では人間くささというか弱さというか、血縁的な継続性(血縁・地縁の第一次集団重視の傾向・・仏教でいう「血脈」)に傾くと人事の固定化がさらに進みます。これは、第二次集団は、個が独立してからの自由な結合関係から成り立ちますが、第一次集団は、個の出生や出身など個の自立性とは無関係なことから成り立っており、そこには人事対流も交流も起こりえないからです。この典型例は、身分制社会での人事固定化ですが、これは、第二次集団からの組織人事運営を行ったヨーロッパ諸国が、第一次集団型の人事を行っていたアジア・アフリカ諸国を支配下に置いたことで勝敗はついています。封建的身分制度の国々が、近代的な人事変革を遂げた西ヨーロッパの国々(中でも先進的なイギリス・・名誉革命でのシステムと人事革新制度)に負けてしまうのは歴史的道理です。卑近でも、経営層が親族系列の人事で失敗したことは分かっていることなのですが、それでも、組織が成功すると、経営層の中には無批判にこの轍を踏んでしまう人もいます。人間的情感の強さというか人材育成の資や視野の狭さというか、でも多くの組織でもまだみられるところですね。
また、近代型の組織での硬直化は、第二次集団の重視の中で起きています。学閥や職場閥というものです。文化伝統を担う学校での学習優秀者や職場経験者からの人事を優先しがちです。これも人事の硬直化のはじまりです。ですが、時としてこれは、一番合理的でなければならない戦闘集団である軍隊でも起こりますと、このピラミッド型の組織故に改革の声も上がりにくく大きな問題となります。これについては、堺屋太一氏の批判をはじめ多くの識者の指摘するところですが、この硬直化した軍隊が敗戦を招くのです。このような人事の硬直化は一定の成長と成功を迎えたほとんどの組織で起こります。その改革は、人事の硬直化が進んでいるだけに行われにくいのです。
・・少し整理・・「人事の硬直化」についての法則について考えると、固定化の強い順は・・「身分制」・「門閥制」・「学閥制」・「職場閥制」となろう・・
「参加者の規格人化」・・システムとして法規遵守を求め、人事としても上層部が制度やきまり重視の特定集団から選出されることとなると、その組織の参加者は、次第に主体性を失っていきます。自分で考えて主体的な判断をしたところで、精緻な法規法令に合致しないと拒否されるし、上層部からは批判され、疎外されるだけということとなります。そういう状況になれば、多くの参加者は、責任を問われないために、自主性を捨てて組織の動きに合わせるだけの人になります。規格人の誕生です。彼らは規格から外れないことで組織の仕事をこなしていきます。これは、きまりの遵守という長所の一方、改革改良もしないという欠点を持ちます。さらには、自分の責任以外の仕事への関わりを捨て、「見ても見えない、知っても知らない」という無関心層を形成します。
以上、システムの硬直化と人材硬直化(上層部と参加者)から、この成功段階の組織はやがて衰退へと向かいます。今日、一定の成功に達した数多くの組織で起きている不祥事、危機管理不足などの背景にはこのような状況があると考えられます。
「図:2つの段階でのシステムと人の状況の比較」

「説明」・・成長段階の「人間くささ」から来る問題行動と成熟後の「官僚的仕組や文化」の中で問題行動とでは、その正確が異なり対応も違ってくる。この対応を誤ると、対応の指導や研修が効果を現さないし、逆な結果も引き起こす。俗に言う「やんちゃや非行」と「陰湿な脳内非行」にも似たものである。組織が成長段階での「やる気のある前傾姿勢でオープンな時代」のルール違反はそれを抑制すればいいのだから「法令遵守」の研修が求められるが、組織の成功期から衰退段階での「自己防衛的で陰湿な時代」のルール違反は水面下での行いが多く、その動機にも暗いものが混じっているので、これには抑制的な研修ではなく 「掘り下げ型の研修」が適している。
それでも、ここまで歪むと修正が難しいので、その前に、組織システムや文化での改善・工夫が求められる。後に触れる「重層柔構造」(自由組織と秩序組織の合体・その結合としての柔軟的な内部組織の整備)がその対応策である。
・・第1話・・終わり